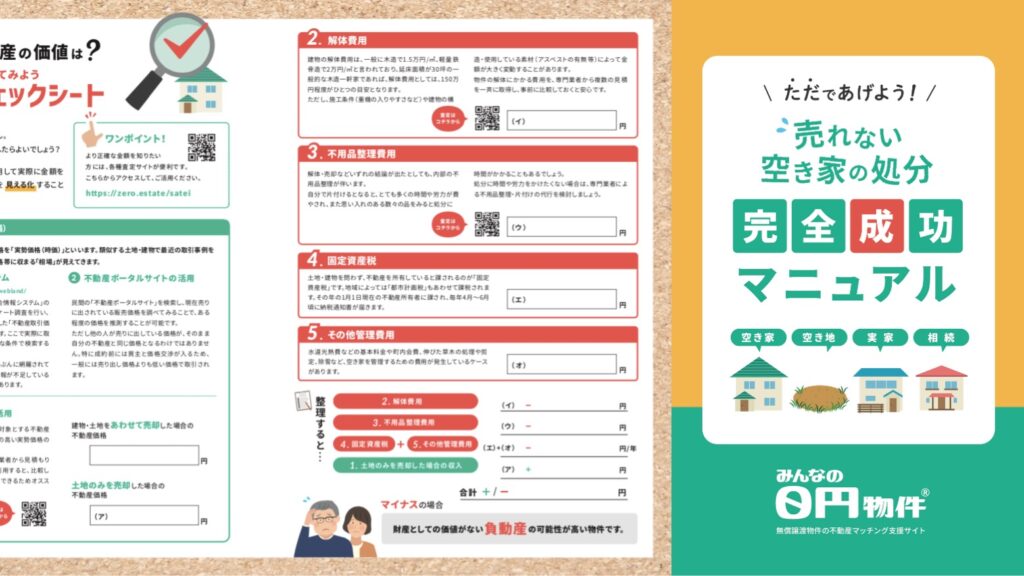取引中止
「無償譲渡でも成立しない」という現実
900万戸
全国の空き家総数(2023年)
13.8%
空き家率(過去最高)
7軒に1軒
が空き家という計算
なぜこのページが重要なのか
無償譲渡、つまり「タダであげる」という条件でも、取引が中止になる物件が存在します。この現実は、日本の不動産問題がいかに深刻であるかを物語っています。
空き家は900万戸を超え、約7軒に1軒が空き家という時代において、不動産は資産ではなく「負動産」となりつつあります。
この一覧を公開する目的は、無償譲渡を検討されている方々に対して、取引が必ずしもスムーズに進むとは限らない現実をお伝えすることです。早期の決断、事前の十分な準備、物件に関する正確な情報開示、そして双方のコミュニケーションが、取引を成功させるために不可欠です。
なぜ無償譲渡でも取引成立しないのか
譲渡側の家族間の意見の相違
物件所有者は手放したいと考えていても、他の相続人や家族が反対するケース。感情的な理由(先祖代々の土地、思い出の家)や、将来的な価値上昇への期待などが背景にあります。
法的問題の発覚
あげたい人とほしい人の双方が取引に合意していても、法的問題により現実的に名義変更が不可能な土地建物が存在しています。農地や借地などは、取引の当事者以外の同意(農業委員会や地権者)が必要になり、頓挫するケースも見られます。
相続放棄という選択
相続人が物件を放棄した場合、所有者不明土地として扱われ、譲渡が進められなくなることがあります。
この場合、譲渡の意思表示ができる人がいなくなるため、無償譲渡の手続きも停止せざるを得ません。
需要がない
譲りたい人がいても、引き取り手が現れないケースも少なくありません。
立地条件、利用制限、修繕負担、固定資産税など、取得後のコストがネックになることが多く見られます。
止まった取引は、個人の重荷と地域の機会損失を生む。
所有者には固定資産税や管理の負担が、地域には活用されない土地や建物が残りつづけます。